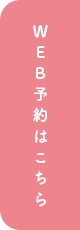Column
コラム
ブラキシズム(歯ぎしり)、こわい!!
- 2023年6月7日
- コラム

みなさん、こんにちは!
今回は私が悩んでいる、ブラキシズム(歯ぎしり)についてお話していこうと思います。
歯ぎしりは歯科では【ブラキシズム】と呼びます。
ブラキシズムといえば、寝てる時にギリギリと音を立てていることを想像されるかなと思いますが、実はブラキシズムは1種類ではなく、日中起きている時にも発生するものなのです。
ブラキシズムの種類
①グラインディング
上下の歯をギリギリと擦り合わせること。
先述した、寝てる時に起きている、ギリギリの音はグラインディングです。
夜寝ている時に起きるグラインディングは、ひとり暮らしなどでは気づきにくく、歯科医院で指摘されて、初めて気づく方もいらっしゃいます。
②クレンチング
強い力で歯を食いしばること。
私はこのクレンチングに悩まされています。
仕事中特に歯石除去などの集中した業務、会議中など、気がつくと上の歯と下の歯が接触していて、時間が経過しているほど、口が開けにくくなっています。
漫画などで何か嫌なことを言われた時に拳を握り、歯を食いしばり、ぐぬぬ…となっているのがクレンチングですね。ぐぬぬと音はなりませんが、力が入っている様がよくわかりますね。
③タッピング
上下の歯を小刻みにカチカチ接触させること。
私の症例経験談になりますが、ブラキシズムの中でも症例としては少ないと思います。
私はまだ出会ったことがありません。。
そもそもどのくらいの力が歯にかかっているか?
グッと力を入れて噛み締めた時、歯にはどのくらいの力がかかっているのでしょうか。
みなさん、わかりますか?
大体70㎏前後と言われています。
日常的に噛むときは、40〜60㎏の力がかかっています。
これは大体、自分の体重に匹敵する力が噛み締めた時に奥歯にかかっていると言われています。
ちなみにギネス記録は180㎏、歯の悲鳴が聞こえてきそう…
ところで、これは意識のある時。
食事をしたり、運動で食いしばった時の負荷です。
寝ている時や無意識のうちにしているブラキシズムは100㎏を超えると言われています。
100㎏の負荷を歯と顎が受け止めているなんて、想像しただけで、顎が疲れてしまいますね。
さて、もう一つ問題です。
歯は上と下、常に接触しているでしょうか??
正解は常にはしていない。
人は安静時2〜3㎜上と下の歯に隙間があって、食事や会話などでも1日に20分程度の接触と言われています。
これを患者さんに説明しているのを、横で聞いていて、私もびっくりしたのをいまだに覚えています。
私は気がつくと上と下の歯が接触していたので、他の人もそうかと思っていたのですが、私が異常だということに気づかされた瞬間でしたね。
ブラキシズムの原因
ブラキシズムには様々な原因があると言われています。
主にストレスや歯並び、遺伝などが原因と考えられていますが、まだまだ議論は尽きません。
今回は、原因をお話しようかと途中まで考えていたのですが、ストレスですよと言ったところで、ストレス発散するしかないだろうし、そんなすぐストレス発散できたら苦労しないので、ブラキシズムを長期間続けるとどうなるのか、治療法はあるのか。について、お話していきます。
ブラキシズムを長期間続けるとどんな影響がでる?
ギリギリするのでなんとなーく、すり減るのかなと考える方が大多数かと思いますが、実はもっと沢山、色んなところに影響がでます。
①歯がすり減る
石臼のように擦っていきますので、段々と歯がすり減っていきます。
②歯がしみる(知覚過敏)
歯が硬いのはエナメル質まで。
象牙質に刺激が通ってしまうと、しみる原因になってしまいます。ヒビが入ったり、露出してしまうとしみる症状がでます。
③歯の根が折れる
歯に強い力が加わることで、竹を割ったように根が割れてしまうことがあります。
④顎関節症
お顔の周りは筋肉で出来ており、食いしばることで咬筋、側頭筋を常に筋トレしている状態になります。
そうすると、顎に過度な負担がかかり、顎関節症になるリスクが高まります。
⑤歯周病が進む
歯周病に罹患している歯はブラキシズムにより、歯周組織の破壊が進んでしまい、歯を支えている骨がなくなって、歯周病が進んでしまうことがあります。
⑥骨が凸凹する
主に下の歯の内側にできやすいです。
(私にもあります…)
これは、下の歯に過度な負担がかかると、骨が歯を守ろうとして、集まってくるイメージ。と私はいつも説明しています。
⑦頭痛、肩こり
ブラキシズムで使う筋肉は、咬筋、側頭筋、首や肩も過緊張になり、慢性的に頭痛や肩こりを訴える方も多いです。(私もそう…)
⑧よく寝れない
自分のブラキシズムの音で起きる方もいるみたい。
治療法
①マウスピース
ブラキシズムによる歯にかかる過度な負担を軽減するために使うものです。
ただ永久的に使うものではありません。
なぜなら、マウスピースを装着することで、上と下の歯の間にマウスピース分の厚みが出来てしまい、噛み合わせの位置が変わってしまうことがあるのです。
マウスピースの使用は、歯科医師と相談しながら使っていきましょう。
②噛み合わせの調整
治療後の補綴物の高さが合っていない、不適合な部分がある場合、噛み合わせの調整、不適合な部分は虫歯のリスクもありますので、再製をご提案しています。
③矯正
ブラキシズムの原因が歯並びにある場合、矯正を行うことで改善することがあります。
④ストレス解消
これは歯科医院でなくても、むしろ歯科医院ではないほうが解消出来るのかもしれません。
歯科医院でも何かお伝え出来ないかと考え、私は患者さんに、マッサージやリラックスの方法をお伝えしています。(自分もブラキシズムしてるのに、お恥ずかしながらお伝えさせていただいております。)
まとめ
ブラキシズムは歯はもちろん、歯以外にも影響を及ぼします。身体にも不調をきたすなんて、ほんと怖い。
最近顎が開けにくい、よく寝れないなど、不調があれば、歯科でもお役に立てることもあるかもしれません。
ぜひ一度、お声かけください。
カテゴリー
最近の投稿
月別アーカイブ
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年7月
- 2021年4月
- 2021年2月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月